【年収450万円の住宅ローン】借入の上限と余裕をもって返せる目安額を解説
最終更新日:

このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
年収が450万円の人は、いくら住宅ローンを借りられるのでしょうか。
金融機関が定める住宅ローンの借入上限額は、年収450万円の場合、約4,400万円です(※)。
※フラット35、金利1.3%、借入期間35年、元利金等返済で試算
4,400万円の住宅ローンを借りると毎月の返済額は約13万円となるため、年収450万円の人にとっては返済が大きな負担となる危険性が高いでしょう。
もし住宅ローンの返済が滞ると最悪の場合、せっかくのマイホームを手放さなければならないことも……。
そのため、年収450万円の人が住宅ローンを借りる際は、借入額2,000万円をひとつの目安にするという考え方もあります。
当記事では、年収450万円における
簡単にまとめると
を解説します。
下記に当てはまる人は、ぜひ当記事で紹介する内容を参考にしてください。
こんな人におすすめ
- 年収450万円で住宅ローンをいくら借りられるのか知りたい
- 年収450万円台の人はどのような住宅ローンを借りているのか知りたい
- 年収450万円でも滞りなく住宅ローンを完済したい
- 住宅ローンの借り入れで失敗したくない

オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士 / 公認会計士中村岳広事務所
監修者千日太郎
公認会計士として、本名である中村岳広の名を掲げた公認会計士 中村岳広事務所を設立・運営。
独自のノウハウと公認会計士としての金融商品の分析力を生かし、
2014年から「千日太郎」として住宅ローンの情報をブログ「千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える」で発信。
「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」では一般の人からの匿名相談に無料で乗り、コンサル内容をネットに公開している。
住宅ローンの金利動向やリスク対策について著した『住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本』など、複数の著書を出版。
▼書籍一覧
住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本
家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本
初めて買う人・住み替える人 独身からファミリーまで 50歳からの賢い住宅購入
住宅破産
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
年収450万円の住宅ローン借り入れ上限額は4,400万円
マイホームの購入を考えている場合「今の年収でいくらまで住宅ローンを借りられるのか」というのは、もっとも気になるポイントですよね。
以下は、年収450万円で借入可能額を試算した結果です。
年収450万円における借入可能額の上限
4,426万円
※フラット35、金利1.3%、借入期間35年、元利金等返済で試算
以上の試算結果から、年収450万円の人は最大で約4,400万円の住宅ローンを借りられることがわかります。
ただし、「約4,400万円」はあくまでもシミュレーションツールの試算結果であり、本当にいくら借りられるのかは、そのときの金利や借入条件によって大きく変わります。
借り入れが可能な額と無理なく返せる額は違う
冒頭でも説明した通り、4,400万円の住宅ローンを借りた場合、月々の返済額は約13万円。
年収450万円の人の手取り月収は約29万円です。
| 年収450万円の人の 手取り月収 | 4,400万円の 住宅ローンの月返済額 |
|---|---|
| 約29万円 | 約13万円 |
実際に年収450万円の人が4,400万円の住宅ローンを借りると、毎月の返済に家計が圧迫されてゆとりのある生活が難しくなる可能性があります。
そのため、「年収450万円では最大4,400万円の住宅ローンを借りられる」という情報を鵜吞みにせず、「無理なく返済できるか」を考えるようにしましょう。
年収450万円で無理なく返せる住宅ローンは約2,000万円
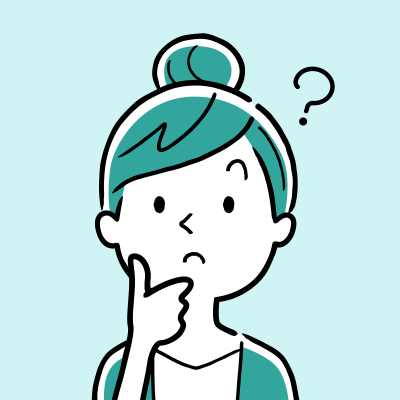
借入可能額の上限である約4,400万円の住宅ローンで生活が厳しくなるのなら、年収450万円で無理なく返せる金額はいくらなの?
年収450万円の場合、無理なく返せる借入額は約2,000万円です。
ただし「年収」と一口に言っても、個々の世帯によって家族構成や収入・支出のバランスは異なるため、年収から算出した借入額が必ずしも正しいわけではありません。
あえて理想的な借入可能額の目安を示すのであれば、年間の返済額が手取り年収の20%以内となる金額になります。
| 年収450万円の手取り年収 | 約350万円 |
|---|---|
| ボーナスなしでの手取り月収 | 約29万円 |
| 手取り年収20%以内の 年間の返済額 | 約70万円 |
| 手取り年収20%以内の 毎月の返済額 | 約58,000円 |
| 返済額から算出した 借入額の目安 | 約2,000万円 |
ゆとりのある生活を送りながら住宅ローンを返済していきたい人は、年間の返済額が手取り年収の20%以内となる借入額を目安のひとつにするとよいでしょう。
ここからは、借入額2,000万円で住宅ローンを利用した場合の返済イメージを、全期間固定金利と変動金利に分けて解説します。

全期間固定金利の場合
借入額2,000万円で全期間固定金利の住宅ローンを借りた場合、以下のような返済イメージとなります。
| 毎月の返済額 | 59,296円 |
|---|---|
| 総返済額 | 24,904,285円 |
※返済期間35年、金利1.3%、元利均等返済
上記のシミュレーション結果から、毎月の返済額は約6万円となり、総返済額は約2,500万円となることがわかります。
変動金利の場合
借入額2,000万円で変動金利の住宅ローンを借りた場合、以下のような返済イメージとなります。
| 1~10年目の返済額 | 51,917円 |
|---|---|
| 11~20年目の返済額 | 58,543円 |
| 21~35年目の返済額 | 62,885円 |
| 総返済額 | 24,574,449円 |
※返済期間35年、
金利1~10年目0.5%
11~20年目1.5%
21~35年目:2.5%
(金利の上昇を想定)、
元利均等返済
金利の上昇を想定すると、月返済額は5万円から6万円に上昇し、総返済額は約2,457万円となることがわかります。
このように、同じ借入額でも金利タイプや適用金利によって、毎月の返済額や総返済額は変わります。
そのため、さまざまな条件でシミュレーションし、ある程度の返済イメージを掴んだうえで、自分にとって適切な借入額を把握するとよいでしょう。
新築・中古のマンション、戸建ての平均額
では、年収450万円で2,000万円の住宅ローンを借りる場合、どのような住宅を購入できるのでしょうか。
まずは、新築と中古の戸建て・マンションの平均的な購入資金を紹介します。
【国土交通省「平成30年度住宅市場動向調査」に基づく平均的な住宅購入資金】
| 戸建て | 新築 | 約3,900万円 |
|---|---|---|
| 中古 | 約2,800万円 | |
| マンション | 新築 | 約4,500万円 |
| 中古 | 約2,800万円 |
上記の表から、新築物件の場合は約4,000万円前後、中古物件の場合は約2,800万円の購入資金が必要になることがわかります。
ただし、上記は平均的な購入費用なので、もちろん購入するエリアや地域によって土地価格は大きく異なります。
返済負担を抑えるポイント
平均的な住宅資金が2,000万円を超えているからと言って、マイホームの購入をあきらめる必要はありません。
ローンの借り入れ金額や返済負担を抑える方法をいくつかご紹介します。
返済負担を抑える方法
- エリアを見直す
- 建築費を抑える
- 中古物件も視野に入れる
- 頭金を多く用意する
返済負担を抑える方法①エリアを見直す
エリアによって土地や物件の値段は大きく異なります。
エリアを見直すことによって予算を抑えられないか、もう一度検討してみましょう。
返済負担を抑える方法②建築費を抑える
戸建て新築の場合、建物の建築費用は工務店やハウスメーカーによって違ううえ、住宅設備や仕様を調整することでも住宅価格は変わります。
無理のない住宅ローン返済計画にするためには、業者の言われるがままになるのではなく、自身の要望と諸条件とをしっかり擦り合わせながら計画を進めていきましょう。
返済負担を抑える方法③中古物件も視野に入れる
中古物件の中には、比較的新しいものや綺麗なものもたくさんあります。
それでいて新築と比べてかなり費用を抑えることができるので、新築でどうしても予算オーバーしてしまう場合は中古物件も視野に入れると良いでしょう。
返済負担を抑える方法④頭金を多く用意する
借入額が2,000万円を超えてしまう分は自己資金で賄うというのも一つの方法です。
ただし、自己資金を使いすぎると将来必要なお金や今後の家の維持費などに影響が出てしまう可能性もあるので注意しましょう。
住宅ローンを途中で返せなくなる典型パターン
年収450万円の人が住宅ローンの借入額を2,000万円に抑えたとしても、途中で住宅ローンの返済が困難になるケースはゼロではありません。
最後に、どうすれば住宅ローンの返済が困難になる事態を防げるのか、途中でローンを返せなくなる典型的なパターンとその対処法を解説します。
ローン返済が困難になるケースと対処法
- 変動金利の金利上昇で返済できなくなる
- 子どもの学資負担で返済できなくなる
困難になるケース①変動金利の金利上昇で返済できなくなる
変動金利は、固定金利と比べて低金利のため、魅力的に見える金利タイプです。
しかし、借入当初から毎月の返済額が家計の大部分を占めているような状態では、金利の上昇に伴って返済額が増えたときに、住宅ローンの返済が困難になるかもしれません。
たしかに、現在の変動金利は低水準です。
とはいえ、これから金利が上がらないとは言い切れず、さらにはどのタイミングで金利が上昇するかもわかりません。

変動金利の金利上昇の対処法
変動金利の住宅ローンを借りたいと思っている人は、「現時点の適用金利から2%上昇しても返済できるか」を基準にして、変動金利でも問題ないか確認する
困難になるケース②子どもの学資負担で返済できなくなる
子どもの学費は、人生における大きな出費のひとつです。
子どもが幼いころからきちんと学費を想定していても、実際に子どもが大きくなって私立の学校や塾に通うようになれば、想定よりも学費が必要になるというケースも多く見られます。
子どもの学費の増大によって家計の収支のバランスが崩れ、住宅ローンの返済が困難になるケースは決してめずらしくありません。
将来の学費負担の対処法
- 子どもが学校に通うまでに十分に貯蓄しておく
- 学費が発生する期間は毎月の返済額が一定になるよう固定金利の住宅ローンを借りる
など、将来のライフプランも見据えて返済計画を立てる
まとめ
年収450万円の場合、借入可能額の上限は約4,400万円ですが、無理なく返せる借入額の目安は約2,000万円です。
しかし、世帯によって収支のバランスやライフスタイルは異なるため、「年収450万円なら借入額は○○万円がよい」と一概に算出することはできません。
さまざまな借入条件で返済をシミュレーションして、自分に合う借入額を見つけましょう。
将来、住宅ローンの返済が困難になる事態を避けるためには、以下の2つを心がけることが重要です。
住宅ローン借り入れで失敗しないために
- 変動金利の低金利が魅力的に感じても、将来金利が上昇したときに対応できるか確認する
- 子どもの学費負担が増えても返済できるよう貯蓄する、あるいは固定金利を検討する
手取り年収の20%に収まる返済額に設定したとしても、今後の収支によっては住宅ローンの返済が困難になることも考えられるのです。
家計の収支バランスや今後のライフプランを踏まえたうえで、自分に合う住宅ローンを探しましょう。


千日太郎 / オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士
【専門家の解説】
住宅ローンのランキングサイトは数多ありますが、その多くは表面的な金利の低さを基準としたものです。
正直なところ、住宅ローンの専門家としてはこうした金利の低さだけを基準に順位付けすることについては、大きな問題があると思っています。
金利が低くても融資手数料が高い銀行があり、その逆もあります。
また、金利上乗せにならない団信の疾病保障が充実している銀行もあるからです。
住宅ローンという商品の良し悪しを測る基準は金利だけでなく「融資手数料」と「疾病保障」があります。
しかし「ランキング」という形式を採る以上は、どれか一つの基準にならざるを得ず、金利の順番になることが多いのです。
そして金利だけで住宅ローンを選ぶのはとても危険です。
最も低金利な金利タイプは「変動金利」ですが、これは銀行の判断により金利を上げることができる契約になっているからです。
どんな場合に金利が上がるのか?そして金利が上昇したら、いくら支払が増えるのか?を知り準備する必要があります。
これに対して「固定金利」は変動金利よりも高い金利となっていますが、その固定期間にわたって金利が上がることはありません。
そのために毎月いくらの支払いが増えるのか?がいわば金利上昇に対する保険料ですね。
こうして、実際に自分が借りようとする金額にあてはめてシミュレーションし、毎月の返済金額として把握したうえで住宅ローンを選ぶようにしてください。















ただし、これはあくまで上限額です。