住宅ローンの金利推移を解説!変動金利は上昇していない?
最終更新日:

このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
長期的にみると、現在の住宅ローンは最低水準の低金利です。
住宅ローンの長期的な金利推移
- 「フラット35」の金利は直近は上昇傾向だが長期的には下がっている
- 「変動金利」の基準金利は横ばいだが、各金融機関の優遇幅が大きくなり、低金利になっている
「今月の金利情報をすぐに知りたい!」という人は、以下から確認してみましょう。
気になる内容をタップ
現在の住宅ローン金利は、最低水準の低金利
住宅ローンの金利は現在、過去最低クラスの低金利になっています。
金利の推移はどの金利タイプを選ぶのかによって異なりますので、ここでは
をそれぞれ見ていきましょう。
フラット35の金利推移【15年前と比較して金利は2分の1に】
フラット35の金利は2022年前半から長期金利の影響により徐々に上昇傾向にあります。しかし、長期的な推移にみると徐々に下降傾向にあり、15年前と比べても約2分の1程度の金利になっています。
なお、適用される金利は毎月更新されるため、月によってやや変動があります。
先月からの金利推移を知りたい方は、フラット35の先月からの金利推移でチェックしてくださいね。
変動金利の金利推移【店頭金利は横ばいだが、適用金利は下がっている】

変動金利の店頭(基準)金利は、直近20年ほどはほぼ横ばいに推移していて、こちらも最低クラスの低金利をキープしています。
さらに、上記のグラフはあくまで住宅ローンの「店頭(基準)金利」を示しており、実際に住宅ローンを借りる際にはここから金利の優遇(割引)を受けられます。
近年、多くの金融機関はこの優遇幅を大きくしているので、実際に借り入れる際の金利はさらに低金利で借り入れできます。
つまり、固定金利を選ぶ場合にも、変動金利を選ぶ場合にも、現在は非常に低金利で住宅ローンを借りられるタイミングといえます。
なお、先月と比較した変動金利の推移は、変動金利の先月からの金利推移でチェックしてください。
すでに変動金利で借りている人は、低金利の恩恵を受けられていない可能性も

近年多くの金融機関で金利の優遇幅が大きくなっているため、店頭(基準)金利が横ばい状態の変動金利でも、実際に適用される金利は低金利になっています。
ただし、すでに住宅ローンを変動金利で借りている人に関しては、銀行のホームページに記載されている金利=あなたのローンに適用されている金利ではないことに注意が必要です。
住宅ローンの適用金利は、基準金利から一定の優遇幅を差し引いて決められますが、この優遇幅は「住宅ローンを借り入れた時点の優遇幅」が適用されます。
つまり、銀行のホームページ上で金利が下がっているように見えても、実際にはあなたの住宅ローンの優遇幅は変わっていないのです。
そのため、すでに変動金利で住宅ローンを借りている人でも、より優遇幅が大きくなっている今、借り換えを行うことで、返済の負担を大きく抑えられる可能性があります。
2024年4月の住宅ローン金利推移・動向
では、より短期的な住宅ローンの金利推移はどうなっているのでしょうか。先月の金利からの推移を見てみましょう。
今月の金利は、10年固定金利、35年固定金利、フラット35で動きが見られました。
金利タイプごとに、金融機関別の住宅ローン金利推移を解説します。
2024年4月の住宅ローン金利推移・動向
変動金利は金利が横ばい
変動金利は、ほとんどの金融機関で金利が横ばいになっています。
複数の金融機関で0.3~0.4%台という記録的な低金利がキープされており、新規借り入れ・借り換えのどちらを検討されている方にとっても低金利のメリットを受けやすいタイミングです。
新規借り入れ
| 金融機関名 | 適用金利 | 前月比 |
|---|---|---|
| PayPay銀行 | 年0.315% 2024年04月適用金利 住宅ローン 自己資金10%以上の場合 | ↑+0.065 |
| 住信SBIネット銀行 | 年0.298% 2024年04月適用金利 WEB申込コース(通期引下げプラン) 自己資金20%以上の場合 自己資金20%未満の場合、表示金利+0.022% | → |
| SBIマネープラザ | 年0.298% 2024年04月適用金利 住信SBIネット銀行 住宅ローン(対面相談コース) 通期引下げプラン 自己資金20%以上の場合 自己資金20%未満の場合、表示金利+0.022% | → |
| auじぶん銀行 | 年0.219% 2024年04月適用金利 全期間引下げプラン 表示金利は新規借入かつau金利優遇割適用。 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 | → |
| ソニー銀行 | 年0.397% 2024年04月適用金利 変動セレクト住宅ローン 新規購入の場合 | → |
| 三井住友信託銀行 | 年0.330% 2024年04月適用金利 住宅ローン 「住宅ローン 家計応援プラン」利用時は、表示金利より0.03%引下げ | ↓-0.075 |
| イオン銀行 | 年0.380% 2024年04月適用金利 金利プラン 物件価格の80%以内でお借入れの場合 | → |
| 三井住友銀行 | 年0.475% 2024年04月適用金利 WEB申込専用住宅ローン 最後までずーっと引き下げプラン | → |
| 三菱UFJ銀行 | 年0.345% 2024年04月適用金利 住宅ローン 適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 | → |
| みずほ銀行 | 年0.375% 2024年04月適用金利 ネット住宅ローン | → |
| 三菱UFJ信託銀行 | 年0.345% 2024年04月適用金利 三菱UFJネット住宅ローン【三菱UFJ信託銀行専用】 | → |
| 楽天銀行 | 年0.583% 2024年04月適用金利 住宅ローン(金利選択型) | ↑+0.027 |
| SBI新生銀行 | 年0.290% 2024年04月適用金利 変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス> 表示金利は金利優遇キャンペーン適用(詳細は公式サイトへ) | ↓-0.13 |
借り換え
| 金融機関名 | 適用金利 | 前月比 |
|---|---|---|
| PayPay銀行 | 年0.349% 2024年04月適用金利 住宅ローン | ↑+0.059 |
| 住信SBIネット銀行 | 年0.320% 2024年04月適用金利 WEB申込コース(通期引下げプラン) 借り換え金利 | → |
| SBIマネープラザ | 年0.320% 2024年04月適用金利 住信SBIネット銀行 住宅ローン(対面相談コース) 通期引下げプラン | → |
| auじぶん銀行 | 年0.198% 2024年04月適用金利 全期間引下げプラン 表示金利は借り換えかつau金利優遇割適用。 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 | → |
| ソニー銀行 | 年0.397% 2024年04月適用金利 変動セレクト住宅ローン 借り換えの場合 | → |
| 三井住友信託銀行 | 年0.330% 2024年04月適用金利 住宅ローン 「住宅ローン 家計応援プラン」利用時は、表示金利より0.03%引下げ | ↓-0.075 |
| イオン銀行 | 年0.380% 2024年04月適用金利 金利プラン | → |
| 三井住友銀行 | 年0.475% 2024年04月適用金利 借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | → |
| 三菱UFJ銀行 | 年0.345% 2024年04月適用金利 住宅ローン 適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 | → |
| みずほ銀行 | 年0.375% 2024年04月適用金利 ネット住宅ローン | → |
| 三菱UFJ信託銀行 | 年0.345% 2024年04月適用金利 三菱UFJネット住宅ローン【三菱UFJ信託銀行専用】 | → |
| 楽天銀行 | 年0.583% 2024年04月適用金利 住宅ローン(金利選択型) | ↑+0.027 |
| SBI新生銀行 | 年0.290% 2024年04月適用金利 変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス> 表示金利は金利優遇キャンペーン適用(詳細は公式サイトへ) | ↓-0.13 |
10年固定金利は金融機関により上下
10年固定金利タイプでは、-0.075%~+0.255%の範囲で金利が上下する金融機関と金利を維持した金融機関に対応が割れました。
10年固定金利は金融機関によって対応が割れる結果になりました、三菱UFJ銀行が1.0%以下の金利を維持し10年固定金利の低さで目立ってます。

10年固定金利 新規借り入れ
| 金融機関名 | 適用金利 | 前月比 |
|---|---|---|
| PayPay銀行 | 年1.085% 2024年04月適用金利 住宅ローン 自己資金10%以上の場合 自己資金なしの場合、記載の金利+0.065% | ↓-0.06 |
| 住信SBIネット銀行 | 年1.198% 2024年04月適用金利 WEB申込コース(当初引下げプラン) 自己資金20%以上の場合 自己資金20%未満の場合、表示金利+0.022% | ↑+0.25 |
| SBIマネープラザ | 年1.198% 2024年04月適用金利 住信SBIネット銀行 住宅ローン(対面相談コース) 当初引下げプラン 自己資金20%以上の場合 自己資金20%未満の場合、表示金利+0.022% | ↑+0.25 |
| auじぶん銀行 | 年1.095% 2024年04月適用金利 当初期間引下げプラン 表示金利は新規借入かつau金利優遇割適用。 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 | ↑+0.01 |
| ソニー銀行 | 年1.290% 2024年04月適用金利 固定セレクト住宅ローン 新規購入の場合 | ↑+0.13 |
| 三井住友信託銀行 | 年1.225% 2024年04月適用金利 住宅ローン 「住宅ローン 家計応援プラン」利用時は、表示金利より0.03%引下げ | ↓-0.075 |
| イオン銀行 | 年1.410% 2024年04月適用金利 当初固定金利プラン | → |
| 三井住友銀行 | 年1.390% 2024年04月適用金利 WEB申込専用住宅ローン 最初にぐぐっと引き下げプラン | ↑+0.25 |
| 三菱UFJ銀行 | 年0.980% 2024年04月適用金利 住宅ローン 適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 | → |
| みずほ銀行 | 年1.400% 2024年04月適用金利 ネット住宅ローン | → |
| 三菱UFJ信託銀行 | 年0.980% 2024年04月適用金利 三菱UFJネット住宅ローン【三菱UFJ信託銀行専用】 | → |
| 楽天銀行 | 年1.690% 2024年04月適用金利 住宅ローン(金利選択型) | ↓-0.044 |
| SBI新生銀行 | 年1.050% 2024年04月適用金利 当初固定金利タイプ 自己資金10%以上 | → |
10年固定金利 借り換え
| 金融機関名 | 適用金利 | 前月比 |
|---|---|---|
| PayPay銀行 | 年1.150% 2024年04月適用金利 住宅ローン | ↓-0.06 |
| 住信SBIネット銀行 | 年1.225% 2024年04月適用金利 WEB申込コース(当初引下げプラン) | ↑+0.255 |
| SBIマネープラザ | 年1.225% 2024年04月適用金利 住信SBIネット銀行 住宅ローン(対面相談コース) 当初引下げプラン | ↑+0.255 |
| auじぶん銀行 | 年1.095% 2024年04月適用金利 当初期間引下げプラン 表示金利は借り換えかつau金利優遇割適用。 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 | ↑+0.01 |
| ソニー銀行 | 年1.290% 2024年04月適用金利 固定セレクト住宅ローン 借り換えの場合 | ↑+0.13 |
| 三井住友信託銀行 | 年1.225% 2024年04月適用金利 住宅ローン 「住宅ローン 家計応援プラン」利用時は、表示金利より0.03%引下げ | ↓-0.075 |
| イオン銀行 | 年1.410% 2024年04月適用金利 当初固定金利プラン | → |
| 三井住友銀行 | 年1.690% 2024年04月適用金利 借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | ↓-0.1 |
| 三菱UFJ銀行 | 年0.980% 2024年04月適用金利 住宅ローン 適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 | → |
| みずほ銀行 | 年1.400% 2024年04月適用金利 ネット住宅ローン | → |
| 三菱UFJ信託銀行 | 年0.980% 2024年04月適用金利 三菱UFJネット住宅ローン【三菱UFJ信託銀行専用】 | → |
| 楽天銀行 | 年1.690% 2024年04月適用金利 住宅ローン(金利選択型) | ↓-0.044 |
| SBI新生銀行 | 年1.100% 2024年04月適用金利 当初固定金利タイプ | → |
全期間固定金利は金融機関により上下、フラット35は金利が下がった
フラット35は、前月に比べて金利が0.02%下がりました。
全期間固定金利は、-0.06%~+0.03%の範囲で金融機関により金利がやや上下しています。
全期間固定金利で金利変動リスクを避け、安心を手に入れたい方は、ぜひ検討したいですね!

全期間固定金利・フラット35(新規借り入れ)
| 金融機関名 | 適用金利 | |
|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 | 年1.750% 2024年04月適用金利 フラット35(保証型) 自己資金20%以上 団信加入 | ↑+0.02 |
| ARUHI | 年1.690% 2024年04月適用金利 ARUHI スーパーフラット ARUHI スーパーフラット8 自己資金20%以上 団信加入 | ↓-0.02 |
| みずほ銀行 | 年1.800% 2024年04月適用金利 ネット住宅ローン | ↑+0.03 |
| 三井住友信託銀行 | 年1.820% 2024年04月適用金利 フラット35 自己資金10%以上 借入期間21年~35年の場合 一般団信加入 | ↓-0.02 |
| SBIマネープラザ | 年1.820% 2024年04月適用金利 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型) 自己資金10%以上 借入期間21年~35年の場合 | ↓-0.02 |
| 楽天銀行 | 年1.820% 2024年04月適用金利 フラット35 自己資金10%以上 借入期間21年~35年の場合 一般団信加入 | ↓-0.02 |
| イオン銀行 | 年1.820% 2024年04月適用金利 イオン【フラット35】 自己資金10%以上 借入期間21年~35年の場合 | ↓-0.02 |
| SBI新生銀行 | 年1.700% 2024年04月適用金利 長期固定金利タイプ | → |
| auじぶん銀行 | 年2.140% 2024年04月適用金利 当初期間引下げプラン 表示金利は新規借入かつau金利優遇割適用。 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 | ↑+0.02 |
| ソニー銀行 | 年2.390% 2024年04月適用金利 住宅ローン 新規購入の場合 | ↑+0.016 |
| PayPay銀行 | 年2.025% 2024年04月適用金利 住宅ローン 自己資金10%以上の場合 自己資金なしの場合、記載の金利+0.065% | ↓-0.06 |
| 三井住友銀行 | 年2.430% 2024年04月適用金利 WEB申込専用住宅ローン 超長期固定金利型プラン | ↑+0.26 |
| 三菱UFJ銀行 | 年1.730% 2024年04月適用金利 住宅ローン 適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 | ↓-0.05 |
全期間固定金利・フラット35(借り換え)
| 金融機関名 | 適用金利 | 前月比 |
|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 | 年1.810% 2024年04月適用金利 フラット35(保証型) 団信加入 | → |
| みずほ銀行 | 年1.800% 2024年04月適用金利 ネット住宅ローン | ↑+0.03 |
| ARUHI | 年1.810% 2024年04月適用金利 ARUHI スーパーフラット 団信加入 | ↓-0.02 |
| 三井住友信託銀行 | 年1.820% 2024年04月適用金利 フラット35 | ↓-0.02 |
| SBIマネープラザ | 年1.820% 2024年04月適用金利 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型) 借入期間21年~35年の場合 | ↓-0.02 |
| 楽天銀行 | 年1.820% 2024年04月適用金利 フラット35 借入期間21年~35年の場合 一般団信加入 | ↓-0.02 |
| イオン銀行 | 年1.820% 2024年04月適用金利 イオン【フラット35】 借入期間21年~35年の場合 Aタイプ(融資手数料定率) | ↓-0.02 |
| SBI新生銀行 | 年1.700% 2024年04月適用金利 長期固定金利タイプ | → |
| auじぶん銀行 | 年2.140% 2024年04月適用金利 当初期間引下げプラン 表示金利は借り換えかつau金利優遇割適用。 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 | ↑+0.02 |
| 三井住友銀行 | 年2.310% 2024年04月適用金利 借り換えローン 超長期固定金利型プラン | ↑+0.01 |
| ソニー銀行 | 年2.390% 2024年04月適用金利 住宅ローン 借り換えの場合 | ↑+0.016 |
| PayPay銀行 | 年2.090% 2024年04月適用金利 住宅ローン | ↓-0.06 |
| 三菱UFJ銀行 | 年1.730% 2024年04月適用金利 住宅ローン 適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 | ↓-0.05 |
フラット35の過去の金利推移を確認したい人は、以下の記事をご覧ください。
金利の推移をみていると、気になるのは「これから金利はどうなるの?」という点ですよね。
次の章では、今後の金利に関してのお話と、もし金利上昇があったときにどう備えるべきかを解説します。
将来の住宅ローン金利予測は意味がない!

金利について一番気になるのは「これから先の金利はどうなるの?」ということですよね。
残念ながら将来の金利は誰にも分かりません。
来月の金利くらいであれば、ある程度の予測をすることは可能ですが、住宅ローンの返済は今後30年以上続けていくものです。
30年後の日本の経済状況がどうなっているのか、それによって住宅ローン金利がどのような影響を受けるのかを予想できる人なんて居ないのです。
大切なのは金利を予測することではなく、金利が上がったときの対策を決めておくことです。
変動金利タイプを選ぶなら、金利上昇時の対策を考えておこう
変動金利タイプを選ぶ際には、金利が上昇した際に「どのような家計への影響があるのか」「金利上昇に備えて準備しておくべきことは何なのか」をしておきましょう。
変動金利には125%ルールと言って、金利が上昇しても毎月の返済額は直前の125%までしか増えないという特徴があります。

つまり毎月返済額に対して25%の貯蓄をしておける人であれば、毎月返済額の上昇には耐えられます。
とはいえ、もちろん家計への負担が大きくなることは間違いないため、毎月返済額が増えたとしても滞りなく返済を続けていけるのかを必ず確認してください。
また、金融機関によっては125%ルールを設けていない住宅ローンもあります。契約する際にチェックしておきましょう。
住宅ローン金利の決まり方
住宅ローンの基準金利の決まり方は変動金利と固定金利でそれぞれ違っていて、変動金利は短期プライムレート、固定金利は新発10年国債利回りを参考にして、銀行が設定しています。
変動金利に影響する「短期プライムレート」とは?
短期プライムレートは、銀行が企業に貸し出す時の最優遇金利で、貸出期間が1年以内のものを指します。
短期プライムレートは日銀の政策金利の影響を受けるため、日銀の政策金利→短期プライムレート→変動金利という流れで影響していきます。
将来的に景気が良くなっていけば、日銀も金利を引き上げることが予想されるので、その際は短期プライムレート、変動金利も上昇していくでしょう。
固定金利に影響する「新発10年国債利回り」とは?
国債とは、国が発行する債券を指します。簡単に言うと借金(の証書)のことですね。
国は債券を発行して投資家の購入資金が入り、投資家は年2回利息を受け取ることができます。
また国債には満期があり、満期になれば国債を購入した際に支払った資金が戻ってきます。この満期には3年や5年、10年などがあり、このうち10年満期の国債利回りを固定金利の参考としています。
なお利回りは価格に対する利息の割合のことです。
住宅ローンを借り換えるべきタイミングとは
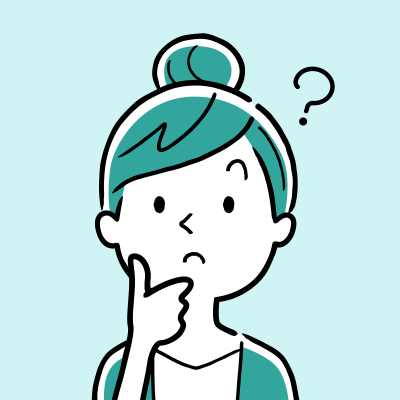
将来の金利は誰にも分からないのなら、住宅ローンの借り換えはいつすればいいの?
利息負担を減らしたいのであれば、今がまさにベストなタイミングです!

現在は変動金利・固定金利の両方で記録的な低金利水準となっているため、借り換えメリットを得やすくなっています。
フラット35からフラット35の借り換えをする場合でも、借り換えによって数十万円~数百万円お得になることも珍しくありません。
残りの返済期間が短くなるほど、借り換えのメリット額も小さくなってしまうので、借り換えの準備はなるべく早く進めていきましょう。
またもしも審査に落ちてしまった時のことも考えて、複数の金融機関に対して事前審査を申し込んでおくこともオススメします。
住宅ローンの審査は複数の銀行に申し込んでもマイナスになることはないですし、審査通過後のキャンセルも可能ですよ。
住宅ローンの金利タイプをおさらい
そもそも住宅ローン金利とは、住宅ローンの借り入れ金額に応じて、借り入れ先に支払う利息を決めるための割合のことを指します。
金利のタイプは、大きく以下の3つに分けられます。
| 金利タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 変動金利 | 返済期間中も金利が変動し、返済額が増減する可能性があるタイプ。 メリット:3つの金利タイプの中で最も金利が低い傾向 デメリット:将来的な金利変動のリスクがある |
| 固定期間選択型金利 (固定金利特約付変動金利) | 固定金利の期間を選べ、期間終了後には再び、変動金利か固定金利を選択できるタイプ。 メリット:全期間固定よりも低い金利で、一定期間金利変動のリスクを抑えられる デメリット:固定期間終了後、再設定するときに金利が上昇することがある |
| 全期間固定型金利 | 返済期間中はずっと借入当初の金利が適用されるタイプ。 メリット:金利変動のリスクなく返済ができる デメリット:3つの金利タイプの中で最も金利が高い傾向 |
それぞれ、メリットとデメリットを理解して、自分のライフプランに合った住宅ローンを選ぶようにしてくださいね。
固定金利か変動金利か、迷ったときの考え方
金利タイプを選ぶ際の基本は、以下の2つの考え方です。
- 金利の上昇前では、固定金利を選ぶ
- 金利が高い時には、変動金利を選ぶ
低金利時に固定金利型のローンを利用すれば、その後金利が上昇しても自身に適用される金利は低いまま。
一方で、高金利時に変動金利型のローンを利用すれば、金利が下がると自身に適用される金利も下がるということですね。
筆者なら保証型のフラット35を選択する
筆者ならどの住宅ローンを借りるのかと聞かれれば、保証型のフラット35を選択します。
将来的に金利が上昇するのか、このまま維持するのかは誰にも分かりませんが、銀行も利益を取らなければならないため、住宅ローン金利が0%を下回ることはありません。
金利がほぼ下限近くまで下がっている今のタイミングで固定金利を選択すれば、完済までの35年間ずっと低金利が適用され続けます。
さらに住宅ローン控除が返済残高の1%なので、実質的に10年間はほぼ利息なしで借りられるようなものです。
※住信SBIネット銀行やARUHIが取り扱っている「独自のフラット35商品」のことを指します。借り入れの際に自己資金を1割以上用意する必要はありますが、従来のフラット35よりも低い金利が適用されるため、返済負担を抑えられるメリットがあります。
低金利の住宅ローンのおすすめ
低金利の住宅ローンのおすすめは以下の3つです。
おすすめの低金利の住宅ローン
auじぶん銀行住宅ローン(変動金利)


- 変動金利
- 全期間引下げプラン
- 年
0.219
%
金利についての注意事項をみる
- ※2024年04月適用金利
- ※表示金利は新規借入かつau金利優遇割適用。
- ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
おすすめポイント
- 01がん50%保障団信+4疾病保障+全疾病長期入院保障が無料付帯
- がんと診断、または4疾病(急性心筋梗塞、脳卒中、肝疾患、腎疾患)が所定の状態に該当・所定の手術を受けた場合、住宅ローン残高が半分になります。さらに全疾病長期入院保障も無料で付帯されます。
- 02がん100%保障の上乗せ金利が低い
- がん100%保障は上乗せ金利年0.2%一般的。auじぶん銀行では100%保障が+年0.05%で付帯できるのでお得。さらに全疾病長期入院保障も無料で付帯されます。
- 03定額自動入金サービスが無料
- メインバンクからauじぶん銀行の口座に毎月自動で入金できるので、返済額を入金する手間がなく、手数料無料でとても便利。
- 04月次返済保障が無料で付帯
- すべてのけが・病気で連続して31日以上入院した場合、住宅ローンの月々の返済が保障される「月次返済保障」も無料付帯。
SBI新生銀行住宅ローン(変動金利)


- 変動金利
- 変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>
- 年
0.290
%
金利についての注意事項をみる
- ※2024年04月適用金利
- ※表示金利は金利優遇キャンペーン適用(詳細は公式サイトへ)
おすすめポイント
- 01ガン団信の上乗せ金利が低い
- 所定のがんと診断された場合に住宅ローン残高が0円になるガン団信の一般的な上乗せ金利は年+0.2%。新生銀行の「ガン団信」なら上乗せ金利が年+0.1%で加入できます。
- 02事務取扱手数料が割安
- 事務取扱手数料が定額で割安なので諸費用を抑えられる※
- 03転職直後でも柔軟に審査してもらえる
- 転職歴の確認や年収見込証明書の提出などの対応をすることで、転職直後でも柔軟に審査してもらえる
- 04つなぎ融資に対応
- つなぎ融資が利用できるので注文住宅にも対応
- ※変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>の事務取扱手数料は借入金額×2.2%(消費税込)
住信SBIネット銀行住宅ローン(変動金利)


- 変動金利
- WEB申込コース(通期引下げプラン)
- 年
0.298
%
金利についての注意事項をみる
- ※2024年04月適用金利
- ※自己資金20%以上の場合
- ※自己資金20%未満の場合、表示金利+0.022%
おすすめポイント
- 0140歳未満なら3大疾病50%保障が基本付帯
- 40歳未満のかたなら「3大疾病50プラン」が金利上乗せなしで加入できます。がん診断時、急性心筋梗塞または脳卒中で所定の手術を受けた場合に住宅ローン残高の50%が保障されます。
- 02全疾病保障が無料で付帯
- すべての病気やケガで働けなくなった場合に住宅ローンの返済が一定期間免除されたり、働けない期間が一定を超えて続いた場合に住宅ローン残高が0円になる「全疾病保障」が無料付帯。
- 03定額自動入金サービスが無料
- 住信SBIネット銀行の口座へ自動で毎月の返済額の入金ができるので、メインバンクを変更しなくてもOK。
- 04金利がネット銀行の中でも特に低い
- 変動金利はネット銀行の中でもトップクラスに低く、フラット35(保証型)も従来のフラット35よりも低金利。
住宅ローン金利についてのよくある質問
- 住宅ローン金利の計算方法は?
住宅ローンの利息を含めた毎月返済額は、「借入金額×{月利(1+月利)返済回数/(1+月利)返済回数-1}」で計算可能です。
しかし計算式が複雑なため、シミュレーションツールを活用して計算するのがおすすめです。
- 住宅ローン金利の相場はどれくらい?
2024年4月時点では多くの金融機関で、変動金利…0.2%~0.5%、固定10年…0.9%~1.7%、固定35年…1.7%~2.4% ほどで設定されています。
それぞれの金融機関での最新の金利は記事内で解説しています。
- 将来の金利はどうなりそう?
将来の金利がどうなるのか、確実な予想をできることはまずありません。
そのため将来の金利がどうなるかではなく、「金利が上がった時にどう対策をするのか」を事前に考えておくことが大切です。 変動金利のリスクや対策については、記事内で詳しく解説しています。
まとめ
住宅ローン金利を選ぶ際に大切なことは、金利タイプごとの特徴を理解して、返済計画を立てておくことです。
金利の上昇が早い段階で起こったとしても、余裕のある返済計画を立てられるのなら変動金利。
金利が上がった場合に余裕が見込めないなら、固定期間選択型や、全期間固定型を選ぶのが一般的にはおすすめです。
ただし一般的に言われていることが全ての人には当てはまらないこともありますので、実際にシミュレーションをして具体的な返済金額を確認してみてくださいね。

千日太郎 / オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士
【専門家の解説】
2022年からは金利の先高観から住宅ローンの固定金利は急激に上昇していますが、変動金利は日銀が金融緩和政策を継続し、政策金利を上げていないことから低金利で横ばいとなっています。
ならば今は変動金利がお勧めか?というと必ずしもそうとは言えません。
メガバンクの三菱UFJ銀行はこれまで変動金利と並んで0.3%台の3年固定金利を主力商品としてきましたが、2022年3
月に0.44%となって変動金利と大差ない水準となり、2022年4月にはホームページのトップページから姿を消しました。
うがった見方をしますと「3年間金利を固定するのであれば変動金利よりも低金利にすることが出来ない」ということなのです。
これに対して変動金利はどの銀行も横ばいですが、この理由は「変動金利は日銀が政策金利を上げたらすぐ上げられますから前もって上げなくてもいい」ということです。
固定金利はその固定期間にわたって金利を固定するため、将来金利が上昇するという観測下では高めに金利を設定しておかなければ、将来銀行が損をしてしまうということになります。
しかし、変動金利は6か月ごとに金利を上昇させることができる金利タイプであるため、実際に日銀が利上げをしてから上昇させれば良いのです。
銀行としては日銀の利上げを前提にした主力商品のラインナップに変えてきているということなのですね。


























具体的な借り入れ金額や、借り換えメリットを調べたい場合にはシミュレーションツールもご活用ください。